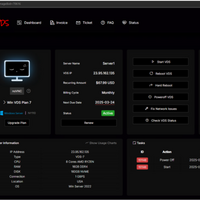9月5日(金)にデジタルアーツ株式会社から編集部宛に届いたプレスリリースにはご丁寧に「(この情報は)9月8日AM9:00まで社外秘情報となります」と小癪(こしゃく)な文言が記されていた。Appleでもあるならともかくデジタルアーツごときが解禁日めいたものを記したという事実に驚いた。
少なくともセキュリティ企業が発信する情報に限って言えば、いわゆる「解禁日時」を設定したプレスリリースの内容が面白かった試しは過去一度もない。ここで面白くなくなる理由を8,000文字程度書く自信はあるが今回はやめておく。
それにしてもデジタルアーツから「~まで社外秘情報」などと記したリリースを受け取るのはここ10年か15年で記者が知る限り初めてのことである。頭の悪いPR会社に踊らされているのではないことは「解禁」などという空疎な言葉の使用を、冒頭のようにクレバーかつ周到に避けていることでわかった。記載も文末にひっそりとである。あちこちに散りばめたりすると頭が悪いと思われることを理解している。
要は情報の内容に同社は自信があるということだ。あるいは沢山の人の目に触れるべきであると考えている。そう推察して、メール本文のリンクからダウンロードしたMicrosoft Wordファイルに目を通したところ、まんまとその通りだとわかった。
とはいえ連絡を受け取った9月には編集部は、1ヶ月まるまる、猛烈に原稿のバックオーダーがたまっていたから「こんな良い内容のリリースなら他誌が記事にするだろう」そう考えて本誌では掲載を見合わせた。しかし、編集部が補足している範囲では10月22日(水)現在、まだどこも記事になどしていない。別にアサヒグループホールディングス株式会社のサイバー攻撃に埋もれてしまったなどということはない。アサヒへのサイバー攻撃の事実が公表されたのは9月29日(月)だ。要はこのリリースの価値をどこの編集部も理解できなかった可能性がある。
確かにわかりづらい内容ではあった。ポイントはサイバー攻撃をしかける奴らとそれを防御する側がまったく同じ武器を使ってタイマンで一騎打ちをして戦い勝利を収めた、あまつさえ個人情報保護委員会がその勝利を認めたという、ざまあみろおととい来やがれ感にあるのだが、おそらくはFinalCodeという製品が超絶マイナーで、誰もそのユニークな機能を知らなかったというのが本当のところだろう。
2024年11月、横浜の保険代理店がランサムウェア攻撃を受けた。しかし、8万件を超える顧客情報は一切漏えいしなかった。攻撃者が暗号化しようとしたデータはすでに国産セキュリティソリューションで暗号化されていたからだ。